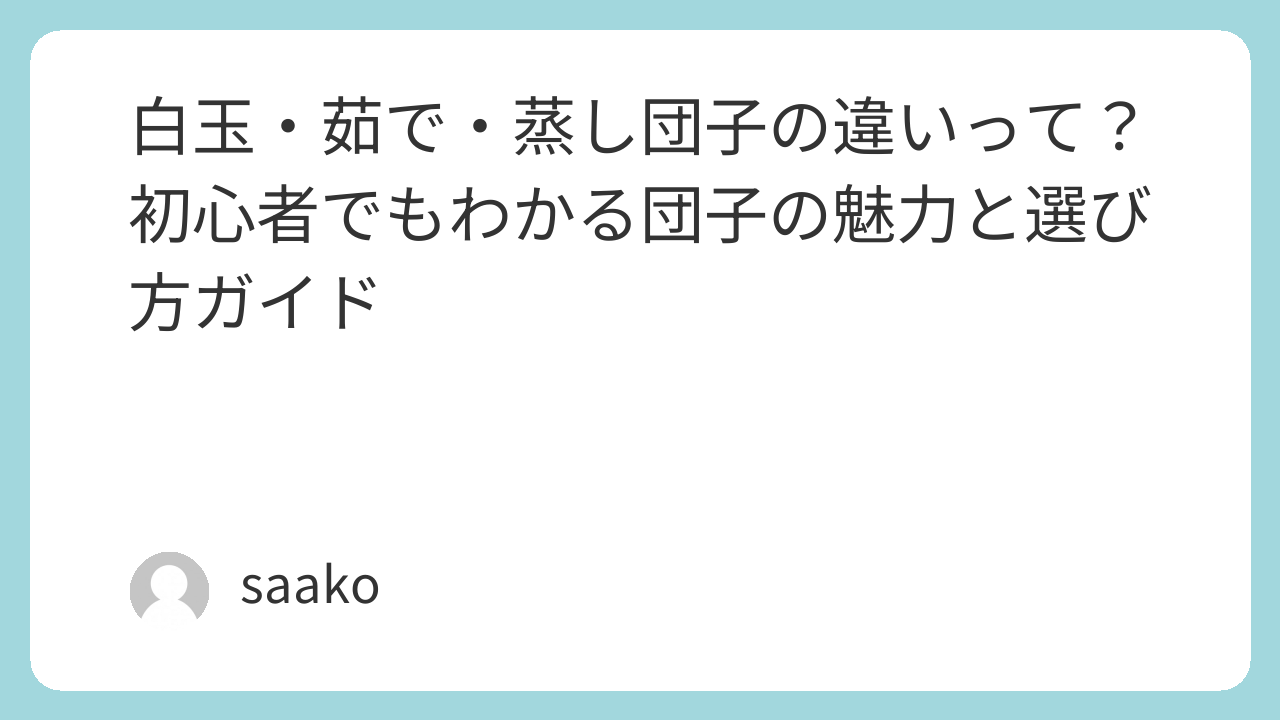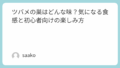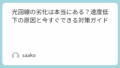ひと口に「団子」と言っても、茹でたり蒸したり、白玉を使ったりと実はいろんな種類がありますよね。
見た目も食感も意外と違っていて、「どれが自分に合ってるの?」と迷ってしまうことも。
この記事では、茹で団子・蒸し団子・白玉団子の違いを、材料・作り方・味や食感の比較をしながら、実際に作って食べてみた感想も交えて詳しくご紹介します♪
初心者さんでも安心して読めるように、保存方法やアレンジレシピ、失敗しないコツもぎゅっと詰め込みました。
お団子作りの参考に、ぜひチェックしてみてくださいね♡
団子の種類と基本的な違い

茹で団子とは?
茹で団子は、その名のとおりお湯で茹でて作る団子のことです。
白玉粉や上新粉などを水でこねて丸めたものを、熱湯でぷかぷか浮いてくるまで茹でて作ります。
家庭でも手軽に作れるので、お子さんと一緒に作るおやつにもぴったり。
茹でることで中まで均一に火が通り、つるんとした口当たりが特徴です。
白玉団子として親しまれていて、あんこやみたらし、きなこをかけて食べるのが定番ですね。
冷やしてもおいしいので、夏場のデザートにもおすすめです。
蒸し団子とは?
蒸し団子は、こねた生地を蒸し器で蒸して作る団子のことです。
もっちり感があり、香りが立つのが特徴です。
茹で団子と比べてやや手間はかかりますが、その分仕上がりに深みが出ます。
蒸すことで素材の風味がしっかり残るので、自然な甘さが引き立ちます。
地域によっては、お祝いごとや仏事など特別な場面で振る舞われることもあり、素朴ながらも伝統的な雰囲気があります。
小豆やさつまいもを混ぜ込んだり、よもぎを加えたりとアレンジも豊富。
白玉団子とは?(茹で団子との違いも解説)
白玉団子は、白玉粉を使って作る茹で団子の一種です。
白玉粉はもち米を粉状にしたもので、これを水と混ぜて茹でると、しっかりとした弾力と、なめらかな舌触りが楽しめます。
通常の茹で団子よりも、やや弾力が強く、つるんとしたなめらかな食感が魅力。
冷やしてもその食感が残りやすいため、和風スイーツやフルーツポンチ、抹茶パフェなどにもよく使われます。
茹で団子という大きなカテゴリの中に含まれる、ちょっと特別な存在といえます。
材料の違いをチェック

茹で団子の材料
・水
材料はとてもシンプル。
ですが水加減によって、仕上がりの柔らかさがかなり変わるので注意が必要です。
水を入れすぎるとゆるくなり、成形しにくくなることも。
市販の団子粉には、うるち米ともち米の粉がブレンドされているものが多く、手軽に扱えて初心者にもおすすめです。
蒸し団子の材料
・砂糖(甘みが欲しい場合)
・水
もち粉を使うとさらにもっちりした食感になります。
甘さを加えたい場合は、砂糖や黒糖を生地に混ぜるとほんのり甘い仕上がりに。
また、よもぎやかぼちゃなどを練り込むと見た目にも彩りが出て、季節感も楽しめます。
白玉団子の材料
・水
・(お好みで砂糖や豆腐)
白玉粉は粒子が細かく、さらさらとしていて扱いやすいのが特徴。
豆腐を混ぜるとより柔らかくなり、冷めても固くなりにくくなります。
この豆腐白玉はヘルシー志向の方や、お子さまのおやつとしても人気です。
作り方の違いを比べてみよう!

茹で団子の作り方
- 上新粉に水を少しずつ加え、耳たぶくらいの柔らかさにこねます。
- 一口サイズに丸めて、沸騰したお湯に入れます。
- 浮いてきたら、さらに1〜2分茹でて、冷水で冷まします。
見た目はころんと可愛らしく、あんこやみたらしとの相性も抜群。
冷やしてフルーツと合わせると夏にぴったりの和スイーツに早変わりします。
蒸し団子の作り方
- 上新粉やもち粉に水を加え、よくこねます。
- 丸めてクッキングシートに並べ、蒸し器で約10〜15分蒸します。
- 表面が透明感を帯びてきたら完成です。
蒸している間、ほんのりお米の香りが広がるのも楽しみのひとつ。
蒸しあがった団子にきなこをまぶしたり、黒蜜をかけるのもおすすめです。
白玉団子の作り方
- 白玉粉に水を少しずつ加えながらこねます。
- 耳たぶくらいの柔らかさになったら丸めます。
- 沸騰したお湯に入れ、浮いてきたら取り出して冷水にとります。
白玉粉は水分を吸いやすいので、一気に水を加えないようにするのがポイント。
冷水に取ることで引き締まり、ぷるんとした食感に仕上がります。
茹で団子の特徴(柔らかさ・保存性など)
・つるんとした喉ごしが魅力。
・冷やしても美味しい。
・翌日にはやや固くなるので注意。
・シンプルだからこそアレンジがしやすい。
蒸し団子の特徴(もっちり感・香りなど)
・もっちり、しっかりとした食感。
・米の風味が残り、自然な甘さも。
・保存性はやや高め。
・香り高く、素朴な味わいが楽しめる。
白玉団子の特徴(弾力・ツルっと感)
・しっかりした弾力。
・なめらかで上品な口当たり。
・冷やしスイーツと相性抜群。
・見た目が美しいので来客時にも◎。
実際に食べ比べ!蒸すor茹でるで団子はどう変わる?

見た目の違いは?
見た目は意外と大きな差があります。
茹で団子はややマットな白っぽさがあり、つるっとしながらもナチュラルな質感です。 白玉団子はさらにツヤツヤしていて、透明感すら感じられるような美しさがあります。
蒸し団子は、ふんわりと膨らんだような素朴な見た目で、手作り感が強く出ます。 ややくすんだ色合いになることもありますが、それもまたほっこりとした魅力です。
パーティーや写真映えを狙うなら白玉、 日常のおやつとしての親しみやすさなら蒸し団子がぴったりですね。
食感の違いは?
茹で団子は、つるんとしたなめらかさが特徴。 口の中でほろっと崩れるような柔らかさもあり、非常に食べやすいです。
白玉団子は、もちっとしつつも弾力が強く、噛み応えがありながらも滑らか。 冷やしてもその弾力が保たれるので、スイーツとの相性が抜群です。
蒸し団子は、もっちり感が際立ち、噛めば噛むほどお米の風味を感じる深みがあります。 昔ながらの素朴なおやつ、という印象を受けます。
どの食感も魅力的なので、「どんな気分か」で選ぶのが正解かもしれません。
味の違いは?
味については、素材そのものを楽しむスタイルか、トッピングに味をゆだねるかで分かれます。
蒸し団子は、香りも含めて素材の風味をしっかり感じられるのが特徴。 砂糖を少し加えた場合でもほんのりした甘さで、どこか懐かしい味がします。
茹で団子や白玉団子は、生地自体に味が少ないぶん、あんこ・みたらし・きなこなどのトッピング次第で無限に味が広がるのが魅力。
白玉はスイーツとしてアレンジしやすく、練乳や果物との相性も◎。
結局どっちがおいしいの?
一概に「これが一番!」とは言えないのが団子の奥深いところ。
さっぱり食べたい日や、冷たいスイーツを楽しみたいときは白玉団子。 懐かしいおやつや、ほっと一息つきたいお茶時間には蒸し団子。
みたらし団子や三色団子など、季節行事や和風のおもてなしには茹で団子がおすすめです。
その時の気分、食べるシーン、そして合わせるトッピングに合わせて、選び分けてみてくださいね♡
どんなシーンで使い分ける?団子の向き・不向き

おやつにおすすめなのは?
冷やして食べられる白玉団子は、おやつタイムにぴったり! 夏にはフルーツと合わせて白玉ポンチにしたり、アイスと一緒に盛り付けても華やかです。
また、白玉は小さなお子さまでも食べやすく、見た目がかわいいので親子で楽しむのにも最適です。
一方、蒸し団子は優しい甘さでボリュームもあるので、小腹が空いたときのおやつにぴったり。 もちもち感がしっかりしているので満足感がありますよ。
おもてなしにおすすめなのは?
見た目の上品さでいえば、白玉団子や蒸し団子が向いています。
白玉団子はつややかで美しく、和スイーツとしてお皿に盛るだけで華やか。 抹茶やほうじ茶と合わせて提供すれば、ちょっとしたカフェ風のおもてなしに。
蒸し団子は、手作り感が出るので、心のこもったおもてなしをしたいときにぴったりです。 黒糖を混ぜて香ばしくしたり、よもぎを練り込んで季節感を出すと、会話も弾みますよ。
保存して翌日食べるならどっち?
翌日のことを考えるなら、蒸し団子が一番おすすめです。
水分が抜けにくく、少し温めなおすだけでももちもち感が戻りやすいです。
茹で団子や白玉団子はどうしても固くなりやすいため、作りたてを食べるのが理想的ですが、冷凍保存して温めなおせばそれなりに美味しくいただけます。
翌日のことを考えて、冷凍向けのレシピで作っておくと便利です♪
一晩置いてもおいしい?翌日検証してみた!

団子って「作ったその日が一番おいしい」とよく言われますよね。 でも、忙しい日常では作り置きしたいこともあるし、食べきれなかった分を翌日においしく食べられたらうれしいですよね。
実際に3種類の団子を作って冷蔵庫で一晩保存してみて、それぞれの変化を観察してみました。
まず、茹で団子は明らかに硬くなりました。 冷蔵庫に入れて数時間で弾力が失われてしまい、噛むとちょっとポソッとした食感に。 温め直しで多少柔らかさは戻りましたが、作りたてのつるん感とはだいぶ違います。
白玉団子も似たような傾向がありました。 ただし、豆腐を混ぜた白玉は冷めても柔らかさを保ちやすく、翌朝でも比較的おいしくいただけました。 「白玉はすぐ固くなる」という印象がある方には、豆腐白玉をおすすめします。
一方、蒸し団子は翌日になってももちもち感がしっかりキープ! レンジで軽く温めるとふっくら感がよみがえり、まるで蒸したてのよう。 香りも変わらず、自然な甘みもそのままでした。
保存性を考えると、蒸し団子が一歩リードという印象です。
団子をおいしく保存する方法

お団子はとても繊細な食べ物。 保存の仕方ひとつで、次の日の味や食感が大きく変わってしまいます。 ここでは、保存する際のポイントを詳しくご紹介します。
常温で置いていいの?
結論から言うと、常温保存は基本的におすすめできません。 特に夏場や梅雨時期は傷みやすく、食中毒のリスクもあるため要注意です。
春や秋などの涼しい時期であっても、長時間の常温放置は避け、なるべく早めに冷蔵庫へ入れるようにしましょう。 「当日中に食べきる場合だけ常温OK」というくらいに考えておくと安心です。
冷蔵保存と冷凍保存の違い
冷蔵保存の場合、1日〜2日以内を目安に食べきりましょう。 保存する際は、乾燥を防ぐためにラップでしっかり包んでください。 ジッパー袋や密閉容器に入れるとさらに◎です。
冷凍保存は、長期保存(約2週間)が可能ですが、解凍後の食感がやや変わってしまう点に注意が必要です。 団子同士がくっつきやすいので、1個ずつラップしてからフリーザーバッグに入れると便利です。
解凍は自然解凍でもOKですが、食べる直前に軽く温めるともちもち感が復活しますよ♪
保存した団子をおいしく食べる温め直し方
・電子レンジ:耐熱皿に団子を並べて、ふんわりラップをかけて10〜20秒ずつ様子を見ながら加熱。
・蒸し器:蒸し団子や冷凍団子には特におすすめ!しっとりふっくら仕上がります。
・お湯でさっと温める:茹で団子や白玉団子にはこの方法も。さっと湯通ししてから冷水に取ると食感が戻ります。
「冷たいままではちょっと…」というときに、ぜひ試してみてくださいね。
団子作りの失敗あるあると解決法

「団子を作ったけど、なんか固い…」 「べちゃべちゃして丸めづらい!」 そんな経験ありませんか?
初めて作るときや、材料の配合をちょっと間違えたときなど、団子作りにはよくある失敗がつきもの。 でも大丈夫!失敗の原因を知っておけば、次からはおいしく作れますよ。
団子が固くなってしまう原因は?
・水分が少なすぎ
・茹ですぎ、蒸しすぎによる加熱のしすぎ
・冷やしすぎて表面が乾燥した
対策:こねるときの水加減を慎重に。 耳たぶくらいの柔らかさを目安にし、水を少しずつ加えるのがコツです。
また、出来上がった団子は乾燥しやすいので、ラップや濡れ布巾で包んで保湿を。
ベタベタしてしまう時の対処法
・水を入れすぎた
・粉と水がしっかりなじんでいない
対策:打ち粉(片栗粉や上新粉)を使って表面のべたつきを抑えましょう。 それでも成形しにくい場合は、ほんの少し粉を足して様子を見てくださいね。
翌日にパサつかせないコツ
・ラップでぴったり包む
・保存容器に乾燥防止用の濡れキッチンペーパーを入れる
・冷蔵より冷凍のほうが食感を保ちやすい場合も
「団子は乾燥との闘い」といってもいいくらい。 ちょっとしたひと手間で、翌日のおいしさに大きな差が出ますよ。
団子をもっと楽しむアレンジレシピ

基本の団子をマスターしたら、次はアレンジに挑戦してみましょう! 見た目も味もガラッと変わって、バリエーションが広がりますよ♪
甘いアレンジ(みたらし・あんこ・フルーツ団子)
甘い団子といえば、やっぱりみたらし団子が王道! しょうゆ・砂糖・片栗粉で作るとろ〜り甘じょっぱいタレをかければ、それだけでお店の味に♡
あんこ団子は、粒あんでもこしあんでもOK。冷たくてもおいしくいただけるので、夏にもぴったり。
白玉団子+カットフルーツ+シロップで作る白玉フルーツポンチも爽やかでおすすめ! 子どもたちのおやつにもぴったりですし、お客様に出しても喜ばれます。
さらに黒蜜やきなこ、抹茶アイスなどを添えると、立派な和風パフェになりますよ。
しょっぱいアレンジ(醤油・鍋に入れる・焼き団子)
団子=甘い、というイメージを覆すのが「しょっぱい系」アレンジ。
焼き団子は、フライパンやグリルでこんがり焼いて、お醤油をひと塗り。 香ばしい香りが食欲をそそります。
また、意外かもしれませんが、小さめに成形した団子を鍋の具材として使うのもおすすめ! もちもちした食感がスープによく合って、冬場にとっても温まります。
お味噌汁に入れるのもアリですよ◎
SNS映えするアレンジ(カラフル白玉・団子パフェ)
最近は「映える」団子がトレンド!
白玉に抹茶・かぼちゃ・紫芋パウダーなどを混ぜてカラフルに仕上げると、見た目も楽しくなります。
丸める形も定番の丸だけでなく、ハート型やお花型にしたり、串に刺してフルーツと交互に並べればカラフル団子串に。
団子パフェは、グラスに白玉・あんこ・アイス・フルーツを重ねるだけで簡単に完成。 和風パフェとしておもてなしにもぴったりです。
団子の地域ごとの違いもチェック!

日本各地には、その土地ならではの団子文化があります。 素材や味付け、行事に合わせた団子など、知れば知るほど奥深い世界です。
関東と関西の団子の違い
一般的に、関東ではしょうゆ味系、関西ではあんこ系の団子が好まれる傾向があります。
例えば関東の「みたらし団子」は、しょうゆの香ばしさが際立つ甘じょっぱいタレが特徴。
一方、関西では「こしあん団子」や「きなこ団子」が多く、優しい甘さを楽しむスタイルが主流です。
また、串に刺すかどうかや団子のサイズも地域で違いが出るので、お取り寄せや旅行先でチェックしてみると面白いですよ。
中国・韓国・台湾の団子文化
日本だけでなく、アジア各地でも団子に似た食文化があります。
中国の湯圓(タンユエン)は、甘いスープに浮かぶ丸い団子で、ゴマあんやピーナッツあんが入っています。
韓国のチョンワンは、カラフルなもち米団子。 祝いごとなどで使われることが多く、日本の団子に近い食感です。
台湾の芋圓(ユーユエン)は、タロイモやさつまいもで作る団子。 QQ食感といわれるモチモチさがクセになります!
こうした他国の団子とも比較すると、団子文化の豊かさがよくわかります。
日本の郷土団子(ずんだ団子・五平餅など)
日本にも魅力的な郷土団子がたくさんあります。
・東北のずんだ団子:枝豆をすりつぶしたずんだ餡が香ばしくて爽やか♪
・岐阜・長野の五平餅:ご飯を潰して平たく伸ばし、クルミや味噌のタレを塗って香ばしく焼きます。
・関西の柏餅や桜餅:端午の節句や春のお祝いに登場する季節団子もおなじみですね。
季節や地域の行事と結びついた団子は、食文化としてもとても奥深いです。 旅行先でご当地団子を探してみるのも楽しいですよ!
まとめ
茹で団子、蒸し団子、白玉団子――それぞれに違った良さがあって、どれも本当に魅力的でした。
つるんと軽やかな茹で団子、ふっくらもっちりの蒸し団子、冷やしても美味しい白玉団子。
その日の気分やシーンに合わせて、使い分けてみるのも楽しいですよ♡
保存やアレンジも工夫しながら、団子ライフをもっと楽しんでみてくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!