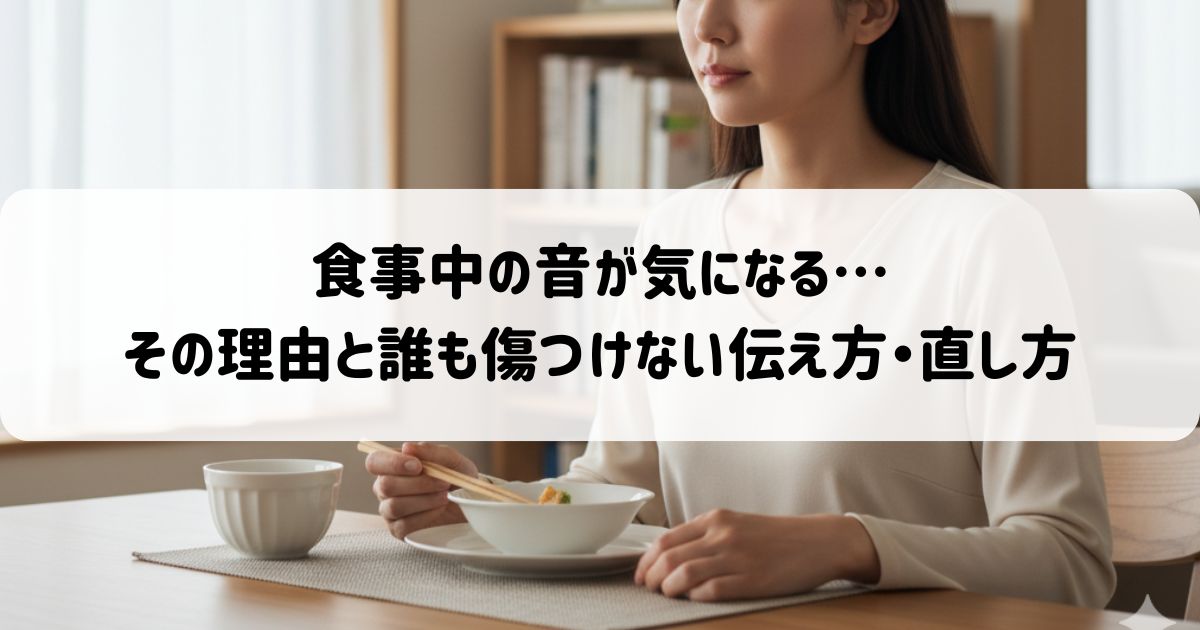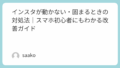食事中に音を立てる、いわゆる「クチャラー」について、誰でも一度は気になったことがあるのではないでしょうか?
「口を閉じて食べて」「音が気になる」といった場面に遭遇したことがある人もいれば、自分が無意識のうちに音を立ててしまっていたという人もいるかもしれません。
この記事では、「なぜ食事中に音が出るのか?」「それは本当に育ちの問題?」「どうしたら改善できるの?」という疑問を、やさしく・わかりやすく解説していきます。
マナーを守りたいけど、どうしたらいいかわからない。そんなあなたのために、今日から実践できるヒントもご紹介します。
他人との関係性をより良くしたい方、自信を持って食事を楽しみたい方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
「食事音=育ちが悪い」というイメージは本当?

クチャラーと呼ばれる人の特徴
クチャラーとは、食べ物を噛むときに口を閉じずにクチャクチャと音を立ててしまう人のことを指します。
口を閉じていないことが多く、咀嚼音が外に漏れてしまうのが特徴です。
この行動が周囲の人に不快感を与えてしまうこともあり、気づかないうちに「マナー違反」と見なされている場合も。
本人は無意識なことも多く、気づいていないケースが少なくありません。
なぜ「育ち」と結びつけられやすいのか
日本では、食事のマナーは家庭教育の一環と考えられています。
そのため、「クチャクチャ音を立てて食べている=マナーを教えられていない」と連想されがち。
「きちんとした家で育っていないのでは?」というイメージが先行してしまうため、社会的にも誤解を生みやすいのです。
しかし、育ちだけで判断するのは少し早計かもしれません。
育ちとマナーは必ずしも同じではない
食事マナーが自然と身につく人もいれば、家庭や文化的な背景からそれを学ぶ機会がなかった人もいます。
マナーを知らなかったからといって、人間性や価値が低いわけではありません。
環境や教育の影響を受けているだけで、後からでもいくらでも学び直すことができるのです。
家庭環境が食べ方に与える影響

親の食事マナーは子どもに受け継がれる
子どもは親の行動を見て学びます。
食べ方もそのひとつ。親が音を立てて食べていれば、それが「普通のこと」として子どもの記憶に残ります。
逆に、親が丁寧に食べている姿を日常的に見せていれば、子どもにも自然とその意識が芽生えるのです。
家庭の食卓は、マナー教育の第一歩とも言えるでしょう。
注意や指導の有無で習慣が変わる
小さい頃から「口を閉じて食べようね」など、優しく繰り返し伝えられることで、食べ方の習慣が作られていきます。
一方で、何も言われずに育つと、正しいマナーを知らないまま大人になることも。
「誰も教えてくれなかったから仕方ない」と感じている人も少なくないはずです。
食卓文化が自然とマナーを形づくる
テレビをつけたままの静かな食事、会話がない食卓、立ったままの「ながら食べ」など、家庭ごとの習慣はさまざまです。
その中で、周囲の人への配慮やマナー意識が育ちにくい環境になっていることも。
明るい雰囲気で会話がある家庭では、「一緒に楽しく食べる」ことを通して自然とマナーが身につく傾向があります。
育ち以外に考えられる要因

身体的特徴(口呼吸・歯並び・鼻づまりなど)
実は、食事中の音が出るのは、体のつくりや健康状態も関係していることがあります。
・鼻づまりで息がしづらく、口呼吸になってしまう
・顎の発達が未熟で、正しく咀嚼できない
・歯並びや噛み合わせの問題で、音が漏れやすい
こういった身体的な理由がある場合、本人の努力だけではどうにもならないケースも。
早めに歯科や耳鼻科など専門医に相談するのもおすすめです。
国や地域ごとの食習慣の違い
文化によって「食事中に音を立てる」ことへの価値観は大きく異なります。
例えば、中国や韓国では、音を立てて麺類をすするのは「美味しい」の証。
タイでは手づかみで食べる文化があり、日本とは違ったマナーが根付いています。
そのため、海外から来た人にとっては、日本のマナーが逆に「静かすぎて落ち着かない」と感じることも。
マナーとは“常識”ではなく“文化”の一部。背景を知ることが理解の第一歩です。
心理的なストレスや無意識のクセ
ストレスが多い日々を送っていると、緊張状態から口周りの筋肉がうまく働かず、気づかないうちに音が出てしまうこともあります。
また、ひとりで食事をする習慣が多い人ほど、周囲への配慮意識が薄れがちです。
「どうせ誰も見てないし」「この方が食べやすいし」と思って続けているうちにクセになってしまうのです。
習慣の積み重ねからくるもの
食べ方のクセは、ある日突然つくものではありません。
小さなクセが何年も積み重なって、「気づいたらクチャラーになっていた」という人も多いです。
長年のクセは直すのに時間がかかることもありますが、意識して少しずつ改善していくことで必ず変化は現れます。
大切なのは、自分のクセに気づくことから始めることです。
日本と海外で異なる「食事音の常識」

日本では「音=マナー違反」とされがち
日本では、「食事は静かに」という文化が深く根づいています。
これは、武士や茶道の文化など、静寂や品格を大切にする日本独特の美意識に由来しているとも言われています。
そのため、音を立てる行為は「周囲への配慮がない」「育ちが悪い」といった印象につながりやすいのです。
そばやラーメンでは音を立てるのが一般的
一方で、日本でも例外があります。
そばやラーメンなどの麺類をすする音は、「おいしさを表現している」「熱いうちに食べている証拠」として、むしろ好ましいとされています。
この習慣があるため、麺類とそれ以外での“音の許容範囲”にギャップが生まれやすく、混乱する人もいるかもしれませんね。
欧米やアジアでの食事音の受け止め方
欧米では、口を閉じて静かに食べることがマナーの基本。
音を立てると「下品」「無神経」と見られることが多く、レストランや家庭でも注意を受けることがあります。
一方、インドやベトナムなどでは、食事中の音を気にしない文化もあり、人それぞれの価値観に基づいて行動しています。
こうした背景を知っておくことで、「なんであの人は音を立てるの?」という偏見を避け、より多様な価値観に対して寛容になれるはずです。
食事音が不快に感じられる理由

ミソフォニアなど脳科学的な背景
実は、「食べる音が気になって仕方がない」という方の中には、ミソフォニア(音嫌悪症)と呼ばれる状態であることがあります。
これは特定の音に対して強い不快感や怒り、焦燥感を覚えてしまう脳の反応です。
食事の咀嚼音、唇をすぼめる音、飲み込む音などがトリガーになることが多く、本人の性格や気分とは関係なく反応が起きてしまうのが特徴です。
「なんでそんなことで怒るの?」と周囲は思ってしまいがちですが、本人にとっては本当にツラいのです。
音に敏感な人とそうでない人の違い
同じ音でも、ある人にとってはまったく気にならないのに、別の人には非常にストレスになるということがあります。
これは、感覚の敏感さや育った環境、過去の経験によっても左右されるもの。
例えば、常に静かな環境で育った人は、些細な音にも敏感に反応しやすくなります。
このように「音の感じ方」には個人差があるため、互いに歩み寄る姿勢が大切です。
不快感が人間関係に与える影響
食事の場面で音が気になりすぎると、相手との会話を楽しめなくなったり、食事の誘い自体を避けるようになったりします。
また、注意したくても「相手を傷つけたくない」「自分が神経質だと思われたくない」と言えず、モヤモヤがたまってしまうことも。
その結果、ストレスが人間関係に影響してしまうこともあるので、お互いに気づき合える関係づくりが大切ですね。
食事音が気になる人に見られる心理傾向

「周囲を気にしていない」と思われやすい理由
音を立てて食べている人を見ると、「なんで気にしないの?」「無神経なんじゃ…」と感じてしまうこともあるかもしれません。
ですが、本人に悪意があるとは限りません。
実際には、自分のクセに気づいていない、または気づいてもどう改善してよいかわからない、という場合も多いのです。
本人には悪気がないケースが多い
「クチャラー」と呼ばれる人でも、わざと音を立てているわけではないことがほとんど。
多くは無意識で、「そんなに音が出ていたなんて知らなかった」という人が大半です。
そのため、感情的に指摘するよりも、冷静に伝えることで相手の気づきにつながりやすくなります。
他人の評価と本人の感覚のギャップ
音を立てている人が「問題ない」と思っていても、周囲は強い不快感を抱いていることがあります。
このギャップが、コミュニケーションのすれ違いや人間関係のトラブルを生み出す原因に。
「自分は大丈夫」と思い込まず、一度自分の食べ方を客観的に見直してみることも大切です。
大人の食事マナーが持つ社会的な意味

「育ちが悪い」と誤解されるリスク
大人になってからも、食事中に音を立てることで「この人、育ちが悪いのかな…」と誤解を招くことがあります。
実際はそんなことないのに、たったひとつの行動で印象がガラリと変わってしまうのは、少し悲しいことですよね。
ですが、それが現実でもあります。
信頼関係やビジネスシーンへの影響
仕事上の食事の場では、相手への印象がとても大切です。
咀嚼音が気になると、「この人、配慮が足りない」「一緒にいて不快」と思われてしまい、信頼関係に悪影響を及ぼす可能性もあります。
とくにビジネスシーンでは、第一印象がその後の関係性を大きく左右するため、マナーには気を配りたいものですね。
人格と結びつけられてしまう問題
食べ方のクセひとつで、「だらしない」「気が利かない」といった印象を持たれてしまうことも。
本当はとても思いやりがある人でも、食事中の行動だけで誤解されてしまうのはもったいないですよね。
だからこそ、自分をよりよく知ってもらうためにも、マナーを意識することはとても大切なことなんです。
食事音を改善するための具体的な方法

自分の食べ方を客観的にチェックする
まず第一歩として、自分の食べ方を見直すことが大切です。
スマホのカメラで動画を撮影したり、鏡の前で食べてみると、自分がどんなふうに口を動かしているかがよくわかります。
音が出ているかどうかは、自分では気づきにくいもの。録音や録画を活用して、客観的にチェックしてみましょう。
家族や信頼できる友人に「音、出てないかな?」と聞いてみるのもおすすめです。
姿勢や噛み方を意識してトレーニング
食べるときの姿勢や、噛むときの口の動きも重要です。
猫背になっていたり、口を大きく開けすぎると音が出やすくなります。
・背筋を伸ばす
・口をしっかり閉じて噛む
・ゆっくり丁寧に咀嚼する
こうした意識を持つことで、食べ方がぐんと上品になります。
はじめは慣れないかもしれませんが、少しずつ習慣づけていくことで、自然に身についていきますよ。
録音・動画で確認する習慣をつける
先ほども触れたように、自分の食べ方を録画して確認するのはとても効果的です。
「こんな音が出ていたんだ…」と驚く方も多いですが、それこそが改善への第一歩。
恥ずかしさよりも、「変わりたい」という気持ちを大切にして、自分のクセを把握していきましょう。
習慣化するには、週に1回だけでもOK。定期的に見返すことで、変化を実感できます。
専門家(歯科・耳鼻科)に相談する
もし、口の閉じ方が難しい、噛みにくい、鼻づまりで口呼吸になるといった症状がある場合は、無理せず専門家に相談しましょう。
矯正歯科や耳鼻咽喉科など、それぞれの専門機関でアドバイスをもらえると安心です。
「自分のせい」と思いすぎず、必要なら医療の力を借りるのも選択肢のひとつです。
子どものうちに身につけたいマナー教育

幼少期から始める「食べ方のしつけ」
小さな頃から食べ方のマナーを伝えていくことはとても大切です。
「口を閉じようね」「音を立てないように食べようね」と、やさしく具体的に声をかけることで、自然と習慣づいていきます。
ポイントは、できなかったときに怒るのではなく、「どうすれば良いか」を一緒に考えてあげること。
マナーは教えるより、一緒に身につけるものです。
叱るよりも一緒に練習するアプローチ
「ダメ!」と頭ごなしに怒ると、子どもは委縮してしまいます。
それよりも、「一緒においしく食べよう」「音を立てないゲームしようか?」など、楽しみながら練習できる工夫をすると効果的です。
おままごとやぬいぐるみとの食事ごっこなどを通して、食べ方を学ぶのもおすすめです。
親が楽しそうに食べていれば、子どもも自然とまねしたくなりますよ。
家庭でできる楽しいマナー習慣
たとえば、週に1回「マナーチャレンジデー」を作って、家族みんなで丁寧な食べ方を意識してみるなど、ちょっとした遊び感覚で取り入れると習慣化しやすいです。
「今日は一番静かに食べられたね!」と褒めるだけでも、子どもにとっては大きな励みになります。
食事の時間が、学びと喜びの場になれば、マナーは自然と育っていくものです。
食事音に悩んだときの対処法(聞く側)

我慢せずにできる工夫
もし身近な人の食事音がどうしても気になるとき、自分の心の中で我慢し続けるのはとてもつらいことです。
まずは、自分が少しでもリラックスできるような工夫をしてみましょう。
たとえば、テレビや音楽をかけて、食事音に意識が集中しすぎないようにするのも効果的です。
また、あらかじめ短めの食事時間にする、同席する回数を調整するなど、自分を守るための“ちょっとした選択”も立派な対処法です。
食事環境を少し変えてみる
食事をする場所や状況を見直すことで、気持ちがぐんと楽になることもあります。
例えば、広めのテーブルに変えたり、椅子の配置を工夫して距離をとったり。
音が響きにくい部屋や、柔らかい素材のマットやカーテンを取り入れることで、音のストレスが軽減されることも。
「環境が変わるだけで、こんなに違うんだ!」と感じる人も多いんですよ。
相手との距離を工夫する
関係性によっては、距離を取ることも必要な場面があります。
毎日一緒に食べる必要がない場合は、少しだけ同席の頻度を減らしてみたり、食べる時間をずらしたりするのも選択肢のひとつです。
無理をして関係をこじらせるよりも、自分の心を守るために「無理しすぎない」姿勢も大切です。
身近な人にやさしく伝える方法

感情的にならず冷静に伝える工夫
大切な相手だからこそ、「食事音が気になる」とはなかなか言いづらいですよね。
でも、ずっと我慢していると、心の中にストレスが溜まり、関係が悪くなってしまうことも。
そんなときは、感情的にならず、落ち着いたタイミングで伝えるのがポイントです。
「実はちょっとだけ気になってて…」とやわらかく話し始めることで、相手も構えずに聞いてくれるはずです。
相手を否定しない言葉の選び方
「クチャクチャしてて気持ち悪い!」などのストレートな言葉は、相手を傷つけてしまいます。
代わりに、「少し音が気になっちゃって…」「私、ちょっと敏感みたいでごめんね」など、自分側の感覚として伝えると角が立ちません。
相手を否定せず、自分の気持ちを素直に伝える表現を選びましょう。
一度で伝わらなくても、焦らずゆっくりコミュニケーションを重ねていけば大丈夫です。
食事環境から改善していく方法
直接伝えるのが難しい場合は、環境の工夫でサポートするのもおすすめです。
・テレビや音楽をつけておく
・静かなレストランではなく、少しにぎやかな場所を選ぶ
・「一緒に丁寧に食べてみよう」など、前向きな提案をする
こうした工夫を通じて、相手に気づいてもらうきっかけをつくることもできます。
まとめ:育ちではなく改善可能性に注目しよう
「育ち」だけで片づけられない理由
食事中の音が気になる・気にされる理由には、たくさんの背景があります。
家庭環境、文化、身体的な特徴、心理的な要因…。
一概に「育ちが悪い」と片づけてしまうのではなく、「何が原因なんだろう?」「どうしたら一緒に改善できるかな?」と考えることが、よりよい人間関係につながります。
快適な食事時間をつくる工夫
「音を立てないように食べる」ことは、思いやりのひとつ。
ちょっとした意識や工夫で、誰でも改善することができます。
自分自身のクセに気づいて変わろうとする人も、周りの人にやさしく伝えようとする人も、それぞれ素敵な一歩です。
お互いを思いやる気持ちがあれば、きっと食事の時間がもっと心地よいものになります。
前向きな姿勢で取り組むことが大切
「マナーって堅苦しい」「注意されるのがイヤ」——そんな気持ちもあるかもしれません。
でも、マナーは“守るため”ではなく“お互いが心地よく過ごすため”のもの。
できることから、前向きに。少しずつ、優しく、変わっていきましょう。
その小さな積み重ねが、あなたの印象や人間関係をより良くしてくれるはずです。